日商簿記3級の概要や合格率を解説|取得のメリットや勉強方法を紹介
日商簿記3級は、経理や財務に限らず、社会人に求められる基礎的な知識や常識を証明できる登竜門的な資格です。
この記事では、日商簿記3級の概要、合格率、難易度について詳しく解説します。また、資格取得のメリットや、合格に必要な勉強時間、効果的な勉強方法についてもわかりやすく紹介します。
この記事を参考に、日商簿記3級の理解を深め、受験対策に役立つ最適な勉強法をぜひ見つけてください。
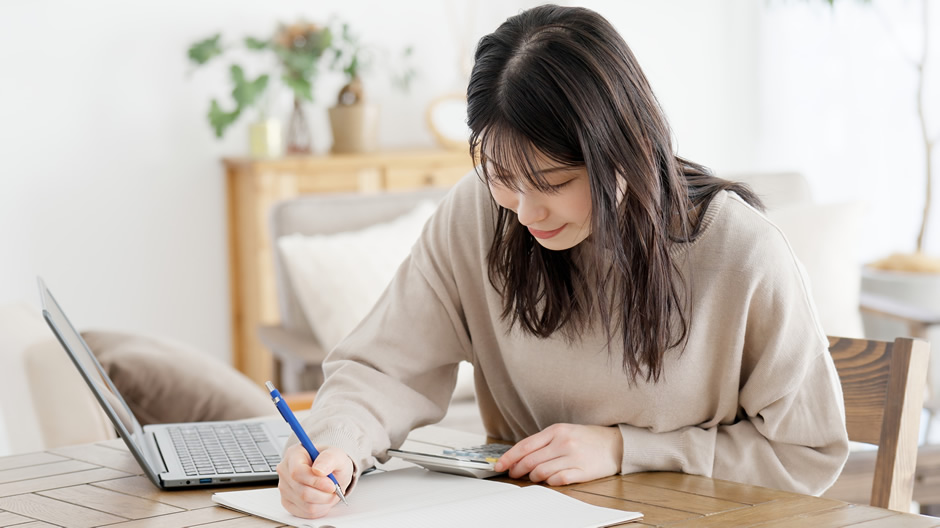
日商簿記3級とは何?

日商簿記3級は、簿記の基礎知識を学べる検定です。日商簿記には、1級から3級のほか、簿記初級や原価計算初級があり、全部で5つの級に分かれています。3級では、一般的な経理業務に必要な仕訳の方法や簿記の基礎概念、貸借対照表などの会計知識を学ぶことができます。なお、2020年12月からは、従来の統一試験に加え、ネット試験も導入されています。
また、日商簿記3級に合格すると、社会人として必要な商業簿記の基礎を習得し、小規模株式会社の経理処理に対応できる基本的なスキルが認められます。この資格は履歴書に記載することも可能です。
日商簿記3級の合格基準と合格率
日商簿記3級の合格基準は、100点満点中70点以上です。そのため、7割以上の正解を目指す必要があります。試験内容は、基礎的な簿記知識を問う問題が大半を占めており、計算問題では、持ち物として認められている電卓の使用が可能です。
2021年から2024年2月までの過去10回分の平均合格率は36.3%ですが、合格率は試験ごとの難易度によって変動し、例年は40〜50%前後で推移しています。また、2020年に始まったネット試験の平均合格率も40.1%で、統一試験と大きな差はありません。
なお、これらの合格率は実際に受験した人に対するものです。会社や学校の関係で申し込みをしたものの、試験日に受験しないケースも多く見られます。
日商簿記3級の難易度が高いポイント
簿記特有の専門用語が多い
日商簿記3級の難易度が高い要因の1つは、簿記特有の専門用語や独特な言い回しが多いことです。
初学者は、簿記を学ぶ際に避けて通れない「仕訳」「勘定科目」「貸借対照表」「損益計算書」といった、日常生活であまり使わない言葉や、「売った」という表現ではなく「商品を引き渡した」といった簿記独特の言い回しに戸惑うことがあります。
これらの専門用語を十分に理解するには、実務経験のない学生はもちろん、社会人であっても多くの時間を要する可能性があります。
覚えるルールや仕組みが多い
日商簿記3級の学習では、以下のほかにも勉強すべき項目が多いことも難易度を高める要因の1つです。
特に「勘定科目」や「仕訳」のルールは、学習初期に押さえておきたい非常に重要なポイントです。しかし、簿記の試験は単なる暗記では対応できません。そのため、簿記の基本的なルールや仕組みをしっかり理解し、応用できるレベルまで知識を深めることが必要です。
- 勘定科目とその分類
- 仕訳のルールと帳簿の記入の仕方
- 貸借対照表や損益計算書の構成 など
実務重視の傾向が強い
以下に示す出題内容と配点からもわかるように、近年の日商簿記3級では、基礎的な実務を想定した問題の割合が増えています。そのため、過去問や参考書に載っていない勘定科目や取引が出題された場合でも、身につけた簿記のルールや仕組みをもとに、自分で予測して仕訳を行う力が求められます。
- 第1問 仕訳問題(15問)/45点
- 第2問 語句記入・補助簿選択・勘定記入(2問)/20点
- 第3問 決算書作成問題(1問)/35点
日商簿記3級を取得する3つのメリット

社会人としての一般常識を理解できる
日商簿記3級の学習内容には、社会人として必須の一般常識が多く含まれています。経済取引を数字で表現する方法やルール、ビジネスの一般的な流れ、さらには「財務諸表」の読み方を理解することができるため、社会人になる前に学んでおくことが有効です。
また、日商簿記3級で得た知識は、営業やマーケティングなど、さまざまな部門で活用することができます。さらに、副業や起業を行う際の確定申告や会計作業をスムーズに進めることができます。
就職や転職のプラス材料になる
日商簿記3級を取得すれば、ビジネスの基礎知識を習得していると企業側から判断され、履歴書ではプラス材料の1つとなります。特に中小企業の経理部門では、日商簿記3級で得た財務諸表を読む力や会計的な視点で経営を分析する力、取引先の経営状況を把握する力が即戦力として評価されることがあります。
また、日商簿記3級の知識を活用すれば、企業の決算書などを分析できるため、就職や転職の際にはエントリー先の見極めにも役立ちます。
上位の資格取得につながる
実際に企業の経理部門で働く場合、日商簿記2級以上の知識が求められることが多くあります。そのため、まずは簿記の基礎知識を定着させるために、3級取得が第一ステップとなります。
また、日商簿記の知識はFP(ファイナンシャル・プランナー)や中小企業診断士の資格取得にも役立つだけでなく、会計に興味を持った場合には、3級の学習内容が基礎となり、税理士や公認会計士などの上位資格にも挑戦しやすくなります。
日商簿記3級取得までの勉強時間の目安
実際の勉強時間は個人の基礎知識や学習速度によって異なりますが、日商簿記3級を取得するために必要な勉強時間の目安は約100時間程度と言われています。つまり、1日約3~4時間勉強できれば、約1ヵ月で合格を目指すことが可能です。
しかし、実際には簿記の勉強に1日2~3時間を充てて、約3ヵ月で合格を目指す方や、仕事や学業がある場合には1日30~60分を勉強に充て、約半年かけて挑戦する人もいます。
また、計画的に学習を進めたい方でも、毎日決まった勉強時間を確保することが難しいこともあります。その場合は、仕事や学業の休憩時間などを利用してこまめに勉強したり、休日に集中して勉強するなど、学習時間を確実に確保する工夫が必要です。
簿記3級の資格がが活かせる仕事
経理・財務
日商簿記3級の資格が活かせる代表的な仕事は、企業の経理部門です。主な業務には、入出金管理、企業間取引の記帳、経営層への会計情報の提供、財務諸表や決算報告資料、財務申告書の作成などがあり、簿記の幅広い知識が役立ちます。
経理部の次に日商簿記3級の知識が役立つのは、財務部です。財務部では、資金調達や資金運用(投資・買収)、財務戦略の立案、予算編成、事業価値の評価などの業務を行います。
ただし、企業の経理や財務の採用条件として、日商簿記2級の資格や同等レベルの簿記知識が求められるケースも多く見られます。
会計・税理士事務所の事務や補助
会計事務所には、簿記3級取得者向けの事務や補助の求人もあります。会計・税理士事務所では、顧客の代わりに「記帳代行」「決算処理」「税務申告」などの経理業務を行うため、経理事務と同様に簿記に関する知識が重要です。
また、会計事務所では経理の観点から顧客にアドバイスを行うこともあり、簿記の知識を活かしながら税務申告全般についての知識と実務経験を積むことができます。また、さらなるキャリアアップを目指す場合には、会計事務所で働きながら日商簿記2級・1級、さらには公認会計士や税理士の資格に挑戦することも可能です。
監査法人の会計監査アシスタント
企業の会計監査を行う監査法人は、主に公認会計士で構成された組織ですが、近年創設された会計監査アシスタントというポジションであれば、実務経験や資格がなくても採用される可能性があります。
会計監査アシスタントの主な仕事は、公認会計士の監査業務のサポートです。公認会計士の指示のもとで業務を行いますが、基礎的な簿記・会計の仕組みを理解している日商簿記3級の取得者は重宝されます。
また、実務経験を積みながら2級以上の簿記資格を取得すれば、より難しい仕事を任せられるようになり、さらなるキャリアアップを目指すことも可能です。
日商簿記3級は独学で合格可能?
前述のように、簿記の勉強は、簿記特有の専門用語やルール、仕組みが多いため、難易度が高く感じられることがあります。しかし、実際の日商簿記3級の合格率は約40〜50%前後と高く、しっかりと試験対策を行えば独学でも合格が狙える資格です。
ただし、日商簿記3級に独学で合格するためには、試験日から逆算して計画的なスケジュールを組むことが重要です。また、参考書や通信教育を活用し、専門用語や簿記の基礎となる仕訳のルールや仕組みを身につけたうえで、過去問などの多くの演習問題に挑戦して知識を定着させることも大切です。
資格取得に向けたおすすめの勉強方法

独学で学ぶ
費用をできるだけ抑えて日商簿記3級試験に挑む場合は、市販のテキストを活用して独学で学ぶことをおすすめします。テキストを購入した日から勉強を始められるだけでなく、仕事や学業のすきま時間を利用して自分の学習ペースで進めることができます。
ただし、独学では自分自身で計画的な学習プランを作成し、進捗管理を行うための強い意志が必要です。また、テキスト選びに迷ったり、間違った箇所を講師や専門家に質問する機会がないというデメリットもあります。
オンライン講座や通信講座で学ぶ
できるだけ独学で合格したいけれど、自分自身だけでは計画的に学習を進めることが難しいと思われる方には、通信講座やオンライン講座での学習をおすすめします。日商簿記3級であれば、高額な費用がかかる可能性は少ないでしょう。
オンライン講座や通信講座では、簿記資格のプロがバランスを考慮し、体系的に学べるカリキュラムを設計しています。さらには、頻出問題や重要なポイントに絞った効率的な学習も実現可能です。また、スマートフォンなどを活用すれば、どこでも勉強を始めることができます。
通学型の資格スクールで学ぶ
簿記学習のモチベーションを維持したい場合は、通学制のスクールを活用することをおすすめします。
自分で教材を選定したり、学習計画を作成する必要がない点や、わからないことがあれば講師に質問できる点、さらに同じ目標を持った仲間と一緒に学ぶことができるのは大きなメリットです。
ただし、独学や通信講座に比べて費用が高いことや、資格スクールの立地によって通学の手間や時間がかかることはデメリットと言えます。
まとめ
日商簿記3級の平均合格率は40〜50%と高く、比較的取得しやすい資格です。まずは、簿記特有の用語やルール、仕組みをしっかりと理解することが重要です。通信講座などを活用し、短期間での合格を目指しましょう。